こんにちは、息子ジロチョの父親、ジロチョdaddyです。
今回は息子の小学校受験を経験を通して、小学校受験のメリットや私立小学校入学後に良かったなと思った事を、息子が入学して1年経った、しかもコロナ禍を経験している今だから言える観点でお伝えしていきたいと思います。
息子が私立小学校に入学して1年経ち、コロナ禍の真っただ中の今、私が感じる小学校受験、私立小学校入学のメリットを以下に挙げます。
1:小学校とアフタースクールの臨時対応力
2:学習習慣が身についた
3:ネイティブスピーカー教師の英語授業
4:体力がついた
5:設備が充実(★プールと図書館)
小学校とアフタースクールの臨時対応力

これは、2020年2月頃から始まったコロナウイルス感染症拡大の社会的な影響が小学校にまで及んだことにより、初めて感じる事が出来た部分だと思います。
小学校に関して大きく影響が出始めたのは、2020年2月27日安倍総理大臣が全国小学校へ休校を要請されたあたりからです。
首都圏の多くの小学校はその休校要請を受け、3月2日頃から最終的には5月31日まで臨時休校が続きました。
そのような状況下で私立小学校に入学してよかったと感じたところが2点あります。
正確な情報・連絡が速やかに保護者に伝わった
1点は、学校としての方針決定が早く、アフタースクールとも上手く連携し正確な情報・連絡が速やかに保護者に伝わった点です。
政府の急な休校要請で学校が休校措置での共働きの我が家は息子をどうするか一瞬迷いました。
私も出張の仕事が入っていて急に仕事を休めないし、妻も休むにしても急には休めない状況でした。
しかし、学校と提携のアフタースクールは2月28日の時点で休校措置に呼応し、3月2日朝から児童を受け入れる臨時対応決定して頂けました。
この時のアフタースクールの対応方針決定のスピード感は賞賛に値するものだと感じましたし、実際助かりました。
私の住んでいる神奈川県の横浜市も公立小学校は休校になりましたが、臨時でまだ年齢的に幼い小学1年生から3年生までを学校で受け入れていました。
ただし、その決定は保護者に届くまで、少なくとも自治体の教育委員会→小学校を経由し保護者に伝わります。
私立小学校は学校単位の権限で対応決定し、即保護者に伝わります。
その構造からもわかる通り、実際にこのような事態になって経験した臨時対応のスピード感と安心感、とにかくはっきりとした情報・連絡が速やかに保護者に伝わった点はメリットだと感じました。
緊急事態宣言が発表された4月7日の時点で、小学校から幾つかの2020年間行事の開催延期・中止状況の連絡があった点も、その意思決定・情報伝達のスピード感を感じることができました。
独自のオンライン授業動画の内容とその構成
もう1点は独自のオンライン授業で学習遅れの縮小と休校明けの学校での学習や生活への連携ができていた事です。
息子の通う小学校でも4月8日頃から動画配信の形でのオンライン授業が始まりました。
live授業とまではいかなかったですが、授業動画の内容は私が予想していたものよりクオリティーが高く、満足のいくクオリティーでした。
社会問題になっていた学習の遅れを少なからず縮小できたと思います。
実は横浜市も市内小学校児童向けに4月初旬から他の自治体と比較して早めの授業動画配信を実施していました。
その動画のいくつかはTVKのテレビ番組としてテレビで放映されていました。
横浜市の小学校に対する対応は意外に早く驚きました。
オンライン授業動画に関して、息子の通う小学校は独自で作成していたので、学校のカリキュラムに即し構成されているのだなと感じました。
これからの学校での生活の説明やソーシャルディスタンスの取り方の動画や保健室からの動画などもアップされており、休校明けの学校での学習や生活をスムーズに執り行える事を意識した独自内容の動画を作成できたのは私立小学校ならではと感じましたは
その成果は本年度の夏休みの短縮期間にも現れているかと考えています。
息子の通う小学校の夏休みは8月1日〜8月26日までに短縮され他のに対し、横浜市の公立小学校は8月1日〜8月16日までの短縮となっています。
学習習慣が身についた

小学校受験の経験を通して実質的一番のメリットは家庭学習習慣が身につく事だと感じます。
小学校によっては考査にペーパー問題を出題しないまたは重要視しないところもありますが、多くの学校がペーパー問題を出題し、一般的には小学校受験準備の大半は、そのペーパー問題対策に追われるものだと私は考えます。
未就学児に他の楽しい遊びやレジャーに使える時間を奪って毎日コツコツ時にはガツガツお勉強させる事は、小学校受験に興味がない方は”酷い”と思われるかもしれません。
我が家でも自発的ではないにしても小学校受験準備中は1年間はほぼ毎日最低でも1日1時間はペーパー問題対策として家庭学習していました。
息子が獲得した、この習慣は小学校入学後も受け継がれています。少なくとも、小学校から帰宅後自宅で楽しい遊びはするものの、必ず短時間ながら勉強もするものという観念が育っているように感じます。
上の章でお伝えしたコロナ休校中のオンライン授業の動画に関しても、自宅で進んで動画視聴学習していました。
ここでさらに考えたいのが、家庭学習習慣が身についたら何が良いのか?
です。私が考える家庭学習習慣が身につく事、身につけるまでのプロセスによって期待できるものを下に記載します。
①:学業成績の向上
②:自制心などの非認知能力を育める
①に関しては直感的にも予測はできるが、近い研究の結果として論文でも発表されています。
国による学習内容の違いがあるものの、学習習慣と学業成績の強い関係が確認されている
奈良教育大学奈 心理学教室 豊田弘司・李 玉然・山本晃輔 著
“日本と中国の子どもにおける学習習慣と情動知能に関する比較研究“より引用
この論文では中国と日本の児童の場合を比較していますが、学習法を考慮する必要はあるかと思うが、国は違えど学習習慣は学業成績を伸ばす要因となっているようだ。
②に関して、非認知能力って何?という方に以下の論文での説明を記載します。
非認知能力とは、IQなどの数値で示される認知能力とは異なり、「学びに向かう力や姿勢」のような「目標や意欲、興味・関心をもち、粘り強く、仲間と協調して取り組む力や姿勢」を中心としたスキルである
名古屋女子大学 伊藤理恵著「保育内容 人間関係」再考:非認知能力を育む保育の観点からより引用
また、非認知能力は私が小学校受験の道を進むきっかけの一つとなった本”「学力」の経済学”の中で、
将来の年収、学歴や就業形態などの労働市場における成果にも大きく影響する事が(研究によって)明らかになってきたのです。
中室牧子著「学力」の経済学 (p86) より引用
実際欧米での非認知能力に関する研究はかなり規模が大きいものまで数多く実施されている注目される能力です。
「学力」の経済学”の中でも重要な非認知能力として「自制心」と「やり抜く力(GRIT)」をあげています。
この自制心、行動観察のスキルや家庭学習で培った、おもちゃで遊びたい気持ちを抑えて毎日コツコツ時にはガツガツお勉強を頑張った事と遜色ないと思います。
幼児にとっては長い試験本番までの受験準備期間、最後まで自分を信じてやりきった事はやり抜く力そのものだと思います。
ネイティブスピーカー教師の英語授業
ほとんどの私立小学校は1年生から英語の授業がカリキュラムに含まれているかと思います。
息子の通う小学校では、1年生からネイティブスピーカー教員による英語の授業があります。
英語教育に注力している学校だと1年生から3コマ以上の授業を設けるところも少なくないです。
民間大手(幼児/児童向け)英会話スクールの月謝はおおよそ7000円程度だと思います。(参照:レスナビ英会話)
それを元に、小学校での英語授業をコスト換算すると
1週間1コマ授業の場合 7,000円×12ヶ月=84,000円
1週間3コマ授業の場合 7,000円×12ヶ月×3=252,000円
単純に比較はできないかとは思いますが、学費にこの料金が含まれていて、しかも小学校の先生なので授業時間以外でも交流がある事を考えたら、その高額と思われる私立小学校の学費のコスト的な面でも見方が変わるのではないかと思います。
体力がついた
体力がついた、これ何で体力がついたの?と思う方が多いと思います。
我が家の場合は、電車とバスを乗り継ぐ通学で体力がついたと実感します。
入学前に一応息子に自宅から1時間弱の通学路を体験させ、「毎日通える?」かを確認した時は「がんばる!」と答えていました。
いざ4月に入学し、電車とバスを乗り継ぐ通学が始まりた当初は、学校から自宅に帰ってすぐ、30分間程度ぐったり制服のまま寝そべって動けない日々が続きました。
2ヶ月程度経ったある日、学校から帰宅した息子は「こんな遠い小学校行ってられない!」みたいな事を言い出していました。
私も迎えに行ける時は極力、途中駅まで車で迎えに行くなどサポートはしていました。
最初は色々愚痴はありましたが、2学期の頃には長い電車とバスを乗り継ぐ通学にも慣れてしまっており、帰宅後は真っ先に騒がしく遊ぶような光景が見られるようになりました。
その体力がわかるのが休日で、いくら一日中外で遊んでも、夜中も体力が有り余り眠れないなんて事も起こったりしています。
ちなみに、電車・バス内では本を読むように誘導し移動時間は読書する習慣がつくという副産物もありました。
設備が充実(★プールと図書館)
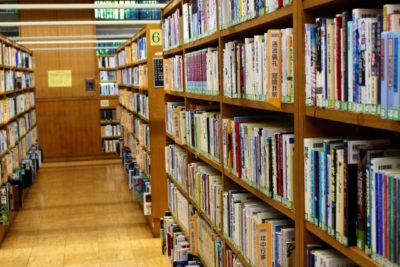
息子が通う小学校の施設として入学後にメリットを感じた設備として、屋内プールと図書館の2点があります。
屋内プール
昨年2019年は梅雨の期間が比較的長く、6月7月の天候に関し、雨の日の比率が多いのが特徴的でした。
雨の関係で水泳の授業が中止になる事が多く、2019年は1回も水泳の授業がなかったというのを聞いたりしました。
息子の通う小学校は屋内プールが完備でしたので、6月から9月まで通常通り水泳の授業を受けていました。
純粋に、毎年天候に影響されず水泳を楽しめる事にメリットを入学初年度から感じました。
ちなみに、夏休みに日程を限定してプールを解放してくれる日もあり、利用する事もありました。
図書館
これは以前書いた記事にも関係しますが、図書館の蔵書数が多く息子が自発的に手を取る本、興味が湧く本がたくさんあった事です。
毎週息子は図書館で本を2、3冊は借りてきて読んでいます。
小学校がカリキュラムの中で読書を誘導するように仕向けているお力添えもあるかと思います。
息子が興味がある本が小学校の図書館にたくさんあって、純粋に家庭で購入する本の費用が浮きますし、探す手間も省けて大助かりです。
何より読書習慣がつく事が一番のメリットだと感じました。
以下の記事で、”学校説明会でのおすすめ質問集、見学の視点”の項目で図書館の蔵書数の事について述べています。
ご参考に。
いかがでしたでしょうか。
個人的な主観で参考にしていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは。

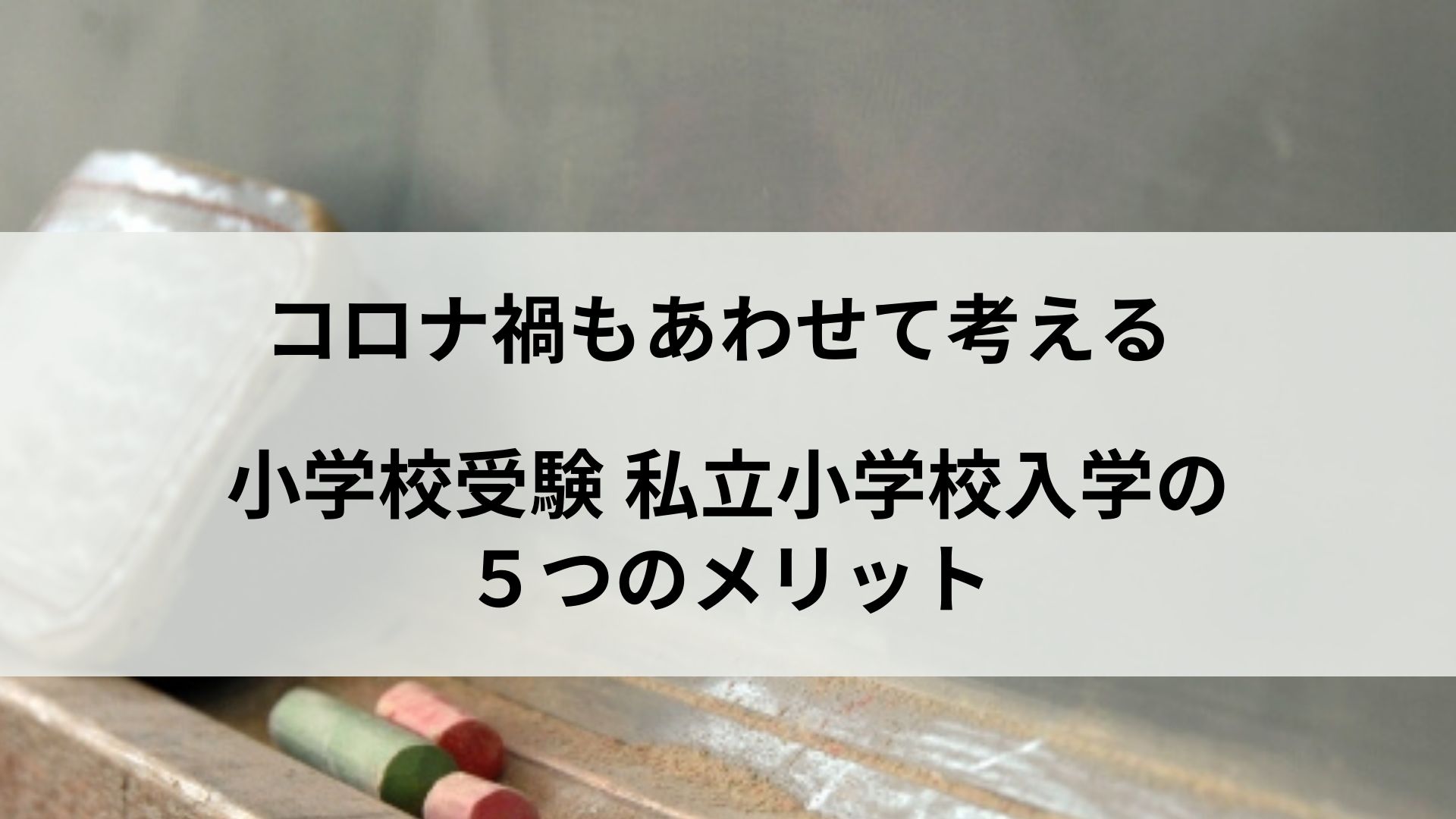
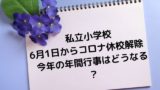


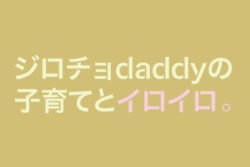
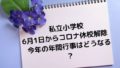

コメント