今回は東京・神奈川の私立小学校で2020年度校長先生が交代された私立小学校の紹介と、我が家の小学校受験時の経験と個人的に感じる注意点をお伝えします。
2020年度校長先生が交代された首都圏私立小学校一覧
| 学校名 | 新しい校長先生のお名前 |
| 学習院初等科 | 大澤 隆之 先生 |
| 国立音楽大学附属小学校 | 千木良 康志 先生 |
| 慶應義塾幼稚舎 | 杉浦 重成 先生 |
| 淑徳小学校 | 松本 太 先生 |
| 帝京大学小学校 | 石井 卓之 先生 |
| 新渡戸文化小学校 | 杉本 竜之 先生 |
| 武蔵野東小学校 | 石橋 恵二 先生 |
| 明星学園小学校 | 剛力 正和 先生 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校 | 村上 公一 先生 |
| LCA国際小学校 | 山口 紀生 先生 |
| 相模女子大学小学部 | 川原田 康文 先生 |
| 湘南学園小学校 | 岸田 修成 先生 |
| 湘南白百合学園小学校 | 谷口 貞女 先生 |
| 桐蔭学園小学校 | 森 朋子 先生 |
校長先生交代における注意点

注意点しておきたいシチュエーションとしては、まず面接時ではないかと思います。
面接時、ストレートに校長先生の名前を質問される事は少ないかと思いますが、入学を希望する小学校の
校長先生の名前を把握しているのは当然だと感じます。
面接官が校長先生だった場合、実際の面接時での面接官からの質問の応答で、校長先生のエピソードなどを話に出す時、校長先生のお名前(苗字)をお付けして話した方が印象は良くなるかと思います。
まして、今年度交代された新しい校長先生の場合はより良いかと個人的には感じます。
例えば話の例として以下の様な話をする時です。
「オンライン学校説明会で校長先生の仰っていた・・・。」
と言うよりかは
「オンライン学校説明会で○○(苗字)校長先生の仰っていた・・・。」
と伝える方が細かい事ですが印象は良くなるかと思います。
なので、前の校長先生の名前と間違える事があってはなりません。
新しい校長先生の名前ははっきりと把握しておく事に越したことはありません。
(合否に影響が出る事は無いと思いますが。。。。)
また、小学校のHPには校長先生の顔写真を掲載されているところもありますので、面接がある小学校でしたら面接の前にお子様とご覧になっておく事をお勧めします。
事前に校長先生のお顔を拝見しておくと、面接官が校長先生だった場合、面接時お子様の緊張も少しは和らぐのではないでしょうか。
校長先生交代にまつわる我が家の経験談

実は我が家も受験年度に校長先生が交代された私立小学校を受験をしました。
当時、校長先生が交代された事自体はもちろん把握していました。
私が直前期に気になっていた事の一つとして、
校長先生の交代で今年度の考査内容が大幅に変更になったりしないか?
という事がありました。
我が家の小学校受験期は各地で開催される合同私立小学校説明会の小学校ブースで直接先生に質問させていただける機会が有りました。
我が家も親子で参加して志望校の先生に何点か質問いたしました。
たまたま対応していただいた担当の方が、その新しく就任された校長先生でした。
私はその質疑応答の時に気になっていた
校長先生の交代で今年度の考査内容が大幅に変更になったりしないか
や
校長先生が交代された事で小学校として何か変化がある様な事はありますか
という事をそれとなく失礼がない様にお聞きしました。
校長先生の返答は
基本的には何が変わる事は無いです。
の様なご返答だったと記憶しています。
話は変わりますが、私立小学校入試の考査内容は毎年、ペーパー問題の問題内容や行動観察のお題や指示などの考査内容は変われど、考査形式(ペーパー問題、行動観察、絵画、個別テストなど)が変更される事はあまりないかと思われます。
個別テストがある小学校では、個別テストの形式が巧緻性系の出題をされたり、面接っぽい事を実施されたり小学校によって毎年同じ形式にそって出題されることが多いです。
上記でお伝えした私立小学校は毎年(過去5年は確実に)個別テストが実施されていて、【お話作り】という形式で毎年出題されていました。
【お話作り】とは、小学性向けの物語本の中の挿絵の様な絵が描いたカードを何枚か提示され、その絵に基づいてオリジナリティーも含め話を作り発表するテストです。
感情を表す言葉など組み込んだり、数枚の絵から話の時系列を考えたりする必要があったりして、幼児にとっては簡単ではない作業だと思います。
息子はこの【お話作り】がどちらかというと得意でした。
幼児教室での模試ではこの分野では3位以内を取っていました。
しかし、蓋を開けてみれば息子の受験年度の考査では毎年出題されていたこの【お話作り】が出題されませんでした。
小学校受験準備期間中、特に入試直前期に息子はお話作りが得意だったのもあり、練習をやりたがり結構な時間を割きました。
我が家の受験年度も確実に主題されるという思い込みもあったので。
校長先生が交代された事と、この毎年考査で出題されていた形式が出題されなかった事は関係がないかもしれませんが...。
こんな事もありましたという経験をお伝えします。
何が出題されなくなる、の対策なんて難しいですが、教訓としては家庭学習時の分野ごとの時間配分はもう少し考える余地はあったなと。
得意を伸ばして自信をつけさせる思いでお話作りの練習に他分野より多めに時間を割きましたが、出題されない可能性を少しでも感じていたら、もう少し他分野の学習にシフトしていたと思います。
特に小学校受験直前期は得意分野、不得意分野関係なく学習時間配分はバランスが重要だと感じます。
我が家の場合の様に、時間を割いても出題されない事があります。


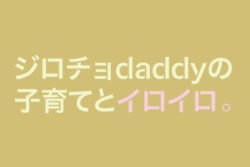

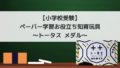
コメント